こんにちは。Emi(@Emi07033909)です。
糖尿病専門医試験対策に糖尿病専門医ガイドブックから、重要事項や、過去に出題された内容をまとめてみました。
参考文献は糖尿病専門医研修ガイドブック第8版からです。
間違いなどあるかもしれません。参照は自己責任でお願いいたします!
DKA
インスリン欠乏下、グルカゴン増加でTG分解、FFAは肝臓で急激な(律速酵素carnitine palmitoyltransferaseIを阻害するマロニルCoAを減少させる。)酸化を受けケトン体を産生する。FFAは食事あるいは脂肪分解から供給さっる。総ケトン>3mmol,3OHBA,AcAc>3になる。
Kussmaul大呼吸=アシドーシスによる呼吸中枢の抑制、代償性の刺激によっておこる大きく深い呼吸。
アシドーシスでは解糖系が抑制、Hb-O2の解離が抑制されている⇒急激なpH補正は組織の酸素供給が障害され、さらに重炭酸イオンを補充するとHCO3-とCo2とではBBBの通過性に差異があり、かえって中枢のアシドーシスを悪化させる可能性がある=paradoxical acidosis
NaとClはほぼ正常かやや低下,Kがやや高値,HCO3-とPaC02は低下する。
ケトーシス:腎臓での尿酸排泄が有機酸による競合阻害で抑制され、高尿酸血症になる
治療:インスリン持続 血糖降下は50-75mg/dl程度とする
水欠乏10ml/kgw(4-10%BW⇒200-500ml/hで補液)、K5mEq/kg補充(→10mmol/hで補液)、Na10mEq/kg
βblockerはDKAでは禁(アシドーシスで心収縮力が抑制されているのをさらに抑制してしまうため)
清涼飲料水ケトーシス
清涼飲料水=10%糖質
ブドウ糖毒性によるインスリン分泌不全とインスリン抵抗性⇒体脂肪の急激な分解と放出された過剰なFFAを基質とするケトン体産生が亢進する。男性が多いが、発症は女性の方が高い。肥満が多い。若年者の方がケトン体産生能が高い。
向精神病薬(食欲↑口渇)との関連も。
合併症:縦隔気腫=Hamman’s syndrome.横紋筋融解症、膵炎様腹部症状、色素性痒疹、一過性尿崩症、舞踏病
Hyperosmoler hyperglycemic state
細胞内脱水、循環虚脱による酸素不足で意識障害。血漿浸透圧による。死亡率16%。脱水による腎血流の低下がブドウ糖排泄を低下させさらに高血糖を増悪する。
浸透圧の計算 2Na+Glu/18+BUN/2.8
水分喪失量:10-15%(⇒15-20ml/kg補液)
誘因:感染、脱水、手術、脳血管障害、薬剤、内分泌疾患、心疾患。
インスリン持続0.025-0.1/kg/h,血糖降下は50-100mg/dl/hぐらい。
代謝性アシドーシス
AG=Na-Cl-HCO3-
乳酸アシドーシス
死亡率25% 乳酸産生:心臓、脳、骨格筋、赤血球、皮膚⇒好気的条件下では肝臓で処理。⇒細胞呼吸障害されるとピルビン酸はTCA回路で酸化されず乳酸に転換されアシドーシスをきたす
診断:血中乳酸>5mmol/l,pH<7.35
- TypeA 組織の循環不全:ショック、低酸素、CO中毒
- TypeB 明らかな組織の循環不全を伴わない
- B1:基礎疾患に続発:DM(インスリン欠乏→PDH↓=乳酸処理↓産生↑+組織の血流障害やRBC2,3diphophoglycerate↓⇒末梢低酸素↑)、肝疾患、悪性疾患、敗血症、褐色細胞腫、チアミン欠乏、尿毒症
- B2:薬物・毒物に関連:アルコール、ビグアナイド、シアン、イソニアジド、サリチル酸、アセトアミノフェン
- B3:遺伝性代謝障害:G6phosphatase deficiency
- B4:その他:低血糖
アシドーシス所見:心収縮力↓心拍出力↓不整脈↑カテコラミン感受性↓細動脈拡張・静脈収縮、肺・腎血流↓肺血管抵抗↑過換気、呼吸筋↓呼吸困難、
インスリン抵抗性、ATP↓K↑蛋白分解↑解糖抑制
注:メイロン投与は逆に肺水腫、高浸透圧、反跳アルカローシスを引き起こすので禁
フェンホルミン:肝ミトコンドリア細胞膜に結合、酸化的リン酸化反応を阻害
⇒メトホルミンでの発症は1/10程度=3/100000
risk eGFR<60+>2000mg/d
2010/5 添付文書 メトホルミン維持量750⇒1500mgに(最大2250mg)
高血糖
- 機能異常:糸球体過剰ろ過、アルブミン尿、血管透過性↑血管弛緩反応↓
- 組織学的異常:細胞外基質↑新生血管、脱髄軸索変性、内膜肥厚
- 細小血管障害:網膜症、腎症、神経障害
網膜症
有病率20%、年3-4%発症
①基底膜の肥厚:aldose reductase, ポリオール経路↑内皮細胞・周皮細胞による細胞外基質過剰産生、アルブミン・フィブリノーゲン蓄積
②毛細血管瘤:眼底検査で最初に確認できる所見。周皮細胞脱落(bysorbitol↑蛋白糖化)による毛細血管壁の脆弱化、血管細胞内接着の消失による内皮細胞の増殖
③内皮細胞の変化;血管透過性亢進。VEGF,PG↓ROS障害で内皮細胞のtight junctionによるblood retinal barrierが崩壊、血管外に赤血球や血漿成分が漏出し網膜出血や硬性白斑(網膜内に漏出した血漿成分が吸収される過程で蛋白や脂質が沈着した結果)。網膜虚血の結果,網膜神経線維層に浮腫を生じたものが,綿花状の軟性白斑
④網膜細小血管閉塞:周皮細胞が脱落すると、血栓傾向、血流障害をきたす。血管新生:網膜虚血でVEGF↑脆弱で容易に破綻=硝子体出血、牽引性網膜剥離、血管新生緑内障
眼底検査、フルオレセイン蛍光眼底造影、光干渉断層計
国際重症度分類ETDRS分類:眼底所見をもとに前増殖糖尿病網膜症への進展の確立
網膜症なし
- 軽症非増殖:毛細血管瘤のみ
- 中等度非増殖
- 重症非増殖:出血、数珠状拡張
- 増殖:新生血管、硝子体出血
Davis分類
- 単純:血管透過性亢進(点状、しみ状、硬性)網膜深層↔表層は神経線維細胞
- 増殖前:軟性白斑、網膜内細小血管異常、血管閉塞、網膜無血管野、静脈の数珠状拡張
- 増殖:血管新生、出血、網膜剥離
新福田分類
- 良性
- A1軽症単純
- A2重症単純
- A3軽症増殖停止
- A4重症増殖停止(陳旧性の硝子体出血)
- A5重症増殖停止
- 悪性
- B1増殖前
- B2早期増殖
- B3中期増殖
- B4末期増殖(硝子体出血)
- B5末期増殖
黄斑浮腫治療
・中心窩を含む⇒抗VEGF. 副作用:血管イベント↑(脳梗塞や心筋梗塞)
・中心窩を含まない⇒網膜光凝固
そのほか抗炎症治療ステロイド(トリアムシノロン)注射もある
光凝固
- 新生血管の発生予防とそれを消退または活動性を低下させることで,増殖前網膜症,増殖網膜症が対象
- 細小血管や毛細血管瘤からの血漿成分漏出を防止することで,主に黄斑浮腫が対象
酸素需要の多い網膜視細胞、網膜色素上皮細胞を破壊することで需要と供給のバランスを是正する。さらに網膜外層の細胞を破壊することで脈絡膜からの酸素を網膜内層に供給できる。VEGFなどの血管新生促進因子の産生が抑制。副作用:夜盲、視野障害、黄斑浮腫、白内障
牽引性網膜剥離となっていたり,硝子体出血=硝子体手術で出血除去,網膜上の増殖組織を除去する術式
増殖網膜症 七里ら。インスリン治療6か月後悪化しやすいHbA1cΔ<1%, >3%で悪化しやすい。低血糖でカテコラミン、トロンボキサン、血小板凝集能の亢進、赤血球酸素解離能の低下をきたすことで毛細血管血流低下から網膜虚血、低酸素が惹起される。
白内障
皮質混濁、後嚢下混濁
CKD
尿所見+eGFR<60が3か月以上
DMN
DM発症から5-10年→微量アルブミン尿→顕性蛋白尿→持続的タンパク尿→腎機能低下→ESRD
1998年から透析導入原因1位、2011年透析維持疾患原因DMN1位(40%)
病理:糸球体肥大、メサンギウム基質増加、結節性病変、滲出性病変、尿細管間質病変
血糖管理、ARBで尿alb患者↓むしろeGFR↓患者↑・・・尿アルブミンを発症する時期が遅くなり、加齢に伴う動脈硬化、尿細管間質線維化がオーバーラップ=DMNと腎硬化症、肥満、脂質異常症、高尿酸血症=糸球体病変よりも尿細管間質・血管病変の進行のため腎機能低下の方が大きい
臨床診断
DM歴5年~, 網膜症・神経障害あり、尿中Albの持続的増加、そのほか糸球体腎炎、腎硬化症、痛風腎の除外、顕著な血尿がない、初期ではeGFR↑腎肥大、高度な腎萎縮を伴わない
分類
腎症前期、早期腎症、顕性腎症、腎不全期、透析療法期
透析予防指導管理料
対象:医師、看護師、保健師、管理栄養士 350点
腎症2期~
2016年腎不全期患者指導加算(eGFR<30腎症患者に運動療法の診療報酬)+100点
2018高度腎機能障害患者指導加算(eGFR<45) DKD予防
腎不全期:残業・夜勤は避ける。
その他
骨格筋でのインスリン抵抗性:受容体以降の異常。そのほかuremia, acidosis, TNFα↑。
通常インスリンは腎臓で40%分解される。尿糖排泄は重度腎機能障害では1/3~1/10に減少する。
DMでは腎性貧血を呈する頻度が非DMに比べて高い。
二次性副甲状腺機能亢進症:P↑⇒FGF23↑⇒VitD活性化阻害PTH↑骨代謝回転が高まる。
4型尿細管性アシドーシスを合併するとK↑
神経障害
Diabetic polyneuropathy
distal axonopathy or dying back axonal degeneration 生命予後↓
手袋靴下型distal symmetric polyneuropathy 小足筋萎縮や足皮膚乾燥、発汗低下⇒前胸部にも感覚低下
大径有髄線維:運動神経、関節位置覚、振動覚、触圧覚
小径有髄線維:痛覚
無髄線維:痛覚、自律神経
感覚⇒自律⇒運動の順に障害される。
DM80%は無症状 有病率20%⇒ATRや振動覚低下を含めると30-40%⇒神経伝導検査:微小遅延電位A波やF波潜時遅延、誘発神経電位振幅低下が90-100%でみられる。
メイヨークリニックによる神経障害リスクは罹病期間、A1c↑、T1DM、網膜症あり。そのほかDLP、肥満、喫煙、高血圧症、心血管疾患でも無症状の小径線維神経障害あり
diabetic multifocal neuropathies
生命予後には影響しない。患者少ない~%。 非対称性の多巣性神経障害
①糖尿病性眼筋麻痺:鈍痛→複視、眼瞼下垂。海綿静脈洞における動眼神経、外転神経の栄養動脈の閉塞。瞳孔機能は保持。数カ月で軽快
②下肢近位筋麻痺:臀部鈍痛→下肢近位筋力↓、歩行困難。腰仙髄神経根(diabetic lumbosacral radiculoplexus )が障害。DM性筋萎縮症急性~亜急性
③体幹神経障害:胸腹部に激痛、胸髄神経根炎
~典型的~
臨床前神経障害:神経症状も障害兆候もないが、電気生理検査で障害が発見される
有痛性神経障害:しびれ、針刺し感=パレステジー、ATR↓振動覚↓
無痛性神経障害: 障害されているが自覚症状がない
廃絶性神経障害:起立性低血圧、排尿障害、脱力、感覚性失調、足病変でQOL、ADL障害
~非典型的~
急性有痛性神経障害:急激な体重減少に続いて四肢下腹部に疼痛。腰仙部神経根・神経叢障害。自律神経症状、髄液蛋白↑脱神経所見。
治療後神経障害:HbA1c月-2%が2-3か月続くとおこる。末梢神経虚血や炎症反応の関与。起立性低血圧や胃腸障害
小径線維神経障害:痛覚低下。鑑別:薬剤、中毒、脊髄空洞症
仮性脊髄癆:下肢感覚性失調。小径線維よりも大径線維が先に障害される。
運動障害型:筋力低下が目立つ
検査
大径有髄線維検査:ATR(感覚神経線維末端部の変性が原因で足けり運動↓膝立ちで検査。背筋や肘の進展運動=Jendrassik増強法)、振動覚(内踝正常10s~.<10低下、<5高度低下。70-80yでは<9,80y~では<8. c64の目盛り5=C128の10s)
小径線維検査:痛覚。楊枝尖端と鈍端を判別できるか。表皮内神経痛覚閾値検査=PINT
圧・触覚:モノフィラメント90°に弯曲する強さ。ティッシュペーパー。痛みが出る場合はアロディニア陽性
小径無髄C線維:自律神経系。CVRR, 起立性低血圧
運動神経障害:足甲部の短趾伸筋萎縮(背屈させて筋腹のふくらみを見る)さらに進行すると、趾背屈障害
潰瘍の前段階=外踝の皮膚角化
NCS:正中・尺骨神経(運動、感覚)、脛骨・腓骨(内踝、運動)、腓腹(外踝、感覚)
運動神経→誘発筋電位CMAP(compound muscle action potential)=M波→遠位・近位の潜時で運動神経伝導速度MCV
F波:脊髄反射由来の筋電位。最短F波潜時が重要。手で20-40m秒,足で40-60m秒。同時に小波Aが記録されることがある=再生神経由来遅発電位=神経線維変性の初期指標。通常は検出されない。
感覚神経活動電位SNAP(近位刺激→末梢で誘導する逆行性測定)→感覚神経伝導速度SCV
正中:CMAP振幅>3mV、潜時<4.0ms、MCV>50m/s、F波最短潜時27.6ms/170cm、SNAP振幅>10µV、SCV>50m/s
尺骨:CMAP>3mV、潜時<3.5ms、MCV>50m/s、F波最短潜時27.6ms/170cm、SNAP振幅>10µV、SCV>50m/s
脛骨:CMAP>5mV、潜時<5.0ms、MCV>40m/s、F波最短潜時50.2ms/170cm、
腓骨:CMAP>2mV、潜時<5.0ms、MCV>40m/s
腓腹:SNAP振幅>5µV、SCV>40m/s
異常所見
- 軽度=速度系;F波最短潜時延長(伝導距離が長いほど測定誤差が小さいので、異常検出感度は最もよい)、MCV/SCV↓、遠位潜時延長
- 中等度=SNAP↓腓腹神経では<10µVで軽度低下、<5µVで確実
- 重度=脛骨神経M波振幅低下=進行期~廃絶期の所見
自律神経検査
心拍変動:1973年Wheeler, Watkins 自律神経障害を有するDM患者においてRRの変動が著明に低下。安静時脈拍増加by副交感神経障害
Ewing法cardiovascular autonomic reflex test CART 深呼気Eで最大、深吸気Iで最小E/I。心拍数で計算することも(異常<10)、起立後心拍変動起立後30拍でHR低下=最大R-R、起立後約15拍でHR増加=最小RR⇒30/15比(異常<1.00)、Valsalva試験40mmHgで15秒間のいきみ。いきみ解除後の最大RRをいきみ中の細小RRで割る。(異常<1.1)
Coefficient of variation of RRintervals 連続した100心拍のRR平均値とSDからCVRRを求める。(副交感神経異常:安静時<2%)
Schellong試験 sBP≧-30, dBP≧-10 交感神経障害を反映。
胃機能検査 迷走神経障害。DM38-65%胃不全麻痺。女性に多い。
ラジオアイソトープ法:99mTC検査食→γカメラでアイソトープ測定。通常4時間以内で胃から排出される。異常は2時間後に胃内容残存率≧60%,4時間後に≧10%
13C呼気テスト:13C検査食→小腸吸収、肝臓代謝で呼気13CO2→peakまでの時間Tmaxを測定
アセトアミノフェン法:胃で吸収されず、小腸で吸収されることを利用。1.5g検査食→血中アセトアミノフェン濃度測定→45分値
腹満感治療:モサプリド 脂質制限
膀胱機能検査 副交感神経障害。初期症状:感覚障害による尿意の低下→膀胱収縮力↓=無力性膀胱。通常の膀胱容量400-500ml⇒これ以上排尿されたら異常。排尿障害治療αblocker, 抗ChE
電流知覚閾値検査by ニューロメーターやペインビジョン。
発汗試験:汗腺=コリン作動性交感神経節後線維Cfiber DM=distal anhidrosis。Sudomotor(発汗促進機能検査)QSART(定量的軸索反射性発汗能検査)やSSR
神経障害鑑別
絞扼性疾患、変形性脊髄疾患、筋疾患、ヘルニア。アルコール・中毒・栄養障害
自律神経障害鑑別:shy drager症候群、アミロイド、傍腫瘍症候群
治療
エパルレスタット(aldose reductase inhibitor=ポリオール代謝抑制)中等度以下で短い罹病機関に有効だが、重症例や長期有病には効果がない。αリポ酸(抗酸化薬)は神経症状と身体所見は改善したが、神経伝導速度低下は改善しなかった。メコバラミン、PG、抗血小板薬も有効性は明らかではない。
有痛性神経障害:NRSやVAS使用
⇒第一選択薬:脊髄後角抑制するCaチャネルα2δリガンド=プレガバリン、ミロガバリン(注眠気、ふらつき、浮腫)
下行性疼痛抑制系を増強するSNRIデュロキセチン、三環系アミトリプチリン(注口渇、尿閉、便秘、眼圧↑=抗コリン作用)
⇒第2選択薬:ワクシニアウィルス接種家兎炎症皮膚抽出液=ノイロトロピン(帯状疱疹後には鎮痛効果があるが、DMにおけるエビデンスはない)、μオピオイド+SNRI=トラマドール
メキシレチン(抗不整脈薬、日本でDM性神経障害に保険適応であるがエビデンスはない)
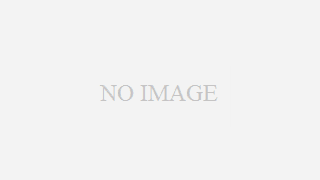












コメント