こんにちは。Emi(@Emi07033909)です。
糖尿病専門医試験対策に糖尿病専門医ガイドブックから、重要事項や、過去に出題された内容をまとめてみました。
参考文献は糖尿病専門医研修ガイドブック第8版からです。
間違いなどあるかもしれません。参照は自己責任でお願いいたします!
肥脂
- 白色脂肪:単房巨大な脂肪滴。寒冷刺激で一部UCP-1=誘導型褐色細胞はBRITE(brown in white)細胞あるいはBeige細胞とよばれる. 脂肪細胞肥大、過形成⇒破綻すると異所性脂肪(肝臓とか)でインスリン分泌障害をきたす
- 褐色脂肪:多房、豊富なミトコンドリア。β3rec UCP-1↑脂肪酸酸化、熱産生↑
肥満に伴う脂肪細胞の肥大化および炎症細胞の浸潤によって恒常性破綻、TNF-α,MCP-1 などの炎症性サイトカインが大量に分泌,肝臓や骨格筋でのインスリンシグナル伝達を障害し,全身でのインスリン抵抗性が悪化する
脂肪組織のTGは再びグリセロール,遊離脂肪酸として血中に放出される.遊離脂肪酸は全身の各臓器におけるエネルギー基質であると同時にインスリン作用およびインスリン合成・分泌にも影響を与え,さらに肥満に伴う過剰な遊離脂肪酸はインスリン抵抗性を悪化させる
肥満・インスリン抵抗性
肝でのlarge TG rich VLDL=VLDL1↑ (インスリンは本来VLDL1合成を抑制するが、抵抗性状態ではその状態が解除される。)一方、small TG rich VLDL=VLDL2は横ばい。
VLDL1はCETPの作用でTGはLDL/HDLに転送される=TGrichLDL/HDL↑
TGはHLで分解sdLDL↑sdHDL↑(=マクロファージからのコレステロール引き抜き能力が低下=動脈硬化疾患に寄与している可能性)
denovo lipogenesis↑(非肥満ではTG合成におけるde novoは5%以下で大半は血中FFAに由来)肥満・インスリン↑では40%近くまで上昇する。内臓脂肪は皮下脂肪に比べてlipolysisしやすい。インスリン自体はlipolysis抑制する
選択的インスリン抵抗性:インスリン抵抗性があればdenovoは低下するはずなのに、実際は亢進。糖代謝だけインスリン抵抗性、脂肪酸合成はインスリン抵抗性を免れている。
- mTORC1 はインスリンシグナルだけじゃなく、アミノ酸でも活性化⇒ChREBP/SREBP1c↑。
- 小胞体ストレスで脂肪酸合成↑。PKCでdenovo↑糖新生↑。
- 門脈血FFA↑=脂肪毒性でインスリン作用減弱、一方中心静脈周囲は脂肪毒性を生じずインスリン感受性が障害されずdenovo↑。Ins↑IRS2↓=糖新生抑制されず高血糖だが、IRS1で制御されるdenovoはインスリンシグナルが伝達され続ける。
インスリン:小腸B48-CM抑制,LPL↑
インスリン抵抗性:B48↑
GLP-1:CM抑制
DM:hepatic lipase↑=HDL↓
コントロール不良DM:TG↑CM↑=Ⅴ型
脂肪萎縮症:白色脂肪↓インスリン抵抗性↑TG↑脂肪肝
黄色腫
コレステロールエステルを多量に含む泡沫細胞の集簇。膝・肘・手指伸展側、アキレス腱。角膜輪。
脂質
LDLは末梢へコレステロールを運搬。HDLは肝臓にコレステロールを運搬
TC, HDLは食前後で変化しにくい
T-Cho=Free Cho+Cholesterol ester
TG=グリセロールに脂肪酸 VLDLやCMに存在。
食後TG↑by80%小腸から分泌されるB48CM
VLDLとCMのTG加水分解経路は競合するため、VLDL↑ればCMの分解は遅延する。
LDL=Friedewald式TC-HDL-TG/5 (TG>400や食後採血では正確に算出できず、nonHDL=TC-HDLが推奨される。
アポタンパク
リポタンパク受容体のリガンドで、リポタンパクの代謝を修飾.
- A-1: HDL LCAT作用。欠損するとHDL↓早発動脈硬化
- B: HDL以外のリポタンパク構成成分。LDL受容体のリガンド。原発性・二次性・家族性複合型高脂血症で上昇。sdLDLと相関。動脈硬化のマーカー
- C-Ⅱ:リポタンパクリパーゼの補酵素、VLDL,CMレムナントなどTGrich lipoproteinのTGの分解を促進する。欠損するとTG↑↑
- C-Ⅲ:LPL活性抑制、apoE阻害。動脈硬化惹起 TGrich lipoprotein↑=C-Ⅱ,Ⅲ↑
- E:LDL以外のリポタンパク受容体のリガンド。TGrich lipoprotein↑で増加、Ⅲ型高脂血症で↑変異でレムナントリポタンパク↑
RLP-C レムナント様リポタンパクコレステロール :LPLによりTGが分解された後異化されずに血中にうっ滞するTGrich lipoproteinの中間代謝産物の総称。CMレムナント、VLDLレムナント(IDL)など。コレステロールに富、小型であるため、動脈壁に侵入しやすく動脈硬化を惹起
酸化LDL=MDA-LDL。マクロファージの泡沫化はLDLではなく、酸化LDLで起こる。
sdLDL:コレステロール含有量が減少、粒子サイズが小型化したLDL。LDL受容体親和性が低下、肝臓での代謝を受けにくく、末梢で取り込まれやすい。酸化変性しやすい。電気泳動上relative migration>0.4で存在が示唆される
Lp(a): LDLを構成するapoB100にapo(a)が結合した蛋白。プラスミノーゲンを競合阻害、血栓傾向↑。年齢や食事、運動に影響されず、遺伝的に決定されるため、個人差が極めて大きい。動脈硬化の危険因子
LPL:血管内皮細胞表面。CM,VLDLのTGを加水分解する。活性にはc-Ⅱが必要。LPL蛋白量測定:ヘパリン静注10-15分後の採血。閉経で増加
LCAT:HDLでFCにFFAを転送してCEを生成し、末梢から肝臓へコレステロールを運搬する。LCAT欠損でHDL↓
脂質異常症
将来動脈硬化性疾患発症を促進させる危険性の高い病的脂質レベルであり、薬物療法を開始するための値ではない
- LDL>140 高LDL血症
- 120-139 境界域高LDLC血症
- HDL<40 低HDLC血症
- TG>150 高TG血症
- nonHDL-C >170 高nonHDLC血症
- 150-169 境界域高nonHDL-C血症
原発性脂質異常症
家族性高コレステロール血症FH
高LDL血症、早発性冠動脈疾患、腱皮膚黄色腫。AD(ホモ1/100万、ヘテロ1/200-500.北陸1/200)。LDL受容体異常(結果apoB100,apoEを含有するリポタンパク異化遅延。VLDL→IDL→LDL↑)やPCSK9機能獲得変異=LDL受容体↓、apoB100 LDL受容体結合部位変異=家族性血管アポリポタンパクB100血症、常染色体劣性遺伝性高コレステロール血症ARH=LDLrec adaptor protein1異常。
初診時LDL>180, FHや早発冠動脈疾患M<55,F<65ならアキレス腱Xp撮影>9mm
治療スタチン、エゼチミブ、PCSK9阻害薬、LDLアフェレーシス
シトステロール血症
AR。シトステロール=植物ステロール↑=動物ステロールの小腸での吸収↑↑肝臓から胆汁への排泄↓↓治療スタチンに抵抗で、レジン、エゼチミブが有効
家族性異βリポタンパク血症(Ⅲ型高脂血症)
apoE↑(ε2/ε2保因+危険因子:DM甲状腺機能低下、肥満、閉経)=LDL受容体結合能↓ Cho↑TG↑レムナント↑=broadβ apoE,B48↑ 皮膚結節性黄色腫、手掌黄色腫。治療コレステロール制限食、スタチン、フィブラート、ナイアシン
家族性複合型高脂血症Ⅱb
食事の影響でⅡaまたはⅣに変動。1/100。思春期以降に発症し、黄色腫はないが、冠動脈疾患を高頻度に合併。VLDL過剰合成。apoB↑、sdLDL↑
LPL欠損症
TG分解できずCM↑Ⅰ型あるいはⅤ型。クリーム状上澄み。膵炎頻回。発疹性黄色腫、網膜脂血症、治療脂肪制限
コレステロール転送蛋白欠損
HDL↑の大部分。ホモ接合体だとHDL130-250、ヘテロで2倍程度に増加。
続発性脂質異常症
- 肥満
- 甲状腺疾患 亢進症LDL↓低下症LDL↑ⅡaⅡb
- Cushing症候群 ⅡaⅡb
- 先端巨大症TG↑HDL↓
- 腎疾患Ⅱb、apoB↑LDL異化↓
- 肝疾患
- 神経性食欲不振症
- Ⅰa型糖原病
- アルコール
- エストロゲン
- チアジド
- βblocker
治療
一次予防3-6か月生活習慣改善。ただしLDL>180では薬物療法考慮
管理目標 低リスク<160, 中リスク<140, 高リスク<120(DM,CKD,PAD,CIはハイリスク)
40-74y リスク評価;tobacco, HTN, HDL↓,耐糖能異常、早発冠動脈疾患
35-74y 吹田スコア
二次予防<100 (FH, ACS, DMhigh(CI,PAD,CKD,metabolic syndrome, tobacco) <70) nonHDL目標はLDL+30 TG<150, HDL>40
日本動脈硬化学会のガイドラインに準じて,糖尿病患者で一次予防の場合には LDL-C 120 mg/dL未満を,冠動脈疾患既往がある二次予防の場合はLDL- C 100 mg/dL 未満を目標としていたが,動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017年版に準じて,糖尿病患者の二次予防でかつ,急性冠症候群やその他のリスク因子(家族性高コレステロール血症 ○非心原性脳梗塞・末梢動脈疾患○細小血管症合併(網膜症・腎症など)○血糖コントロール不良状態の持続 ○メタボリックシンドローム ○主要危険因子の重複 ○喫煙)を有している場合は,LDL-C 70 mg/dL 未満を目標とすることを推奨している
Cho<200mg ショ糖、単糖、果糖はTG↑ アルコール<25g/日 食物線維>25g/日
動物性脂肪飽和脂肪酸↓=LDL↓心血管イベント↓ただし極端に少ないと脳出血↑ ⇒総エネルギー4.5-7%で飽和脂肪酸摂取
n-3多価不飽和脂肪酸リノレン酸EPA,DHA⇒TG↓インスリン抵抗性改善血小板凝集抑制、血管内皮機能改善
運動でHDL↑
治療薬
- 妊娠希望にはレジン
- HMGCoA還元酵素阻害薬:コレステロール合成抑制、LDL受容体合成↑副作用:肝障害、ミオパチー
- 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬:エゼチミブNPC1L-1阻害 K吸収↓=ワーファリン作用増強
- 陰イオン交換樹脂レジン、コレスチラミン 腸肝循環阻害だが、肝臓での合成亢進するためスタチンとの併用がのぞましい
- プロブコール LDL↓HDL↓ LDL受容体を介さず胆汁酸にコレステロール排出 CETP
- ニコチン酸 LPL活性化、ホルモン感受性リパーゼ抑制。
- フィブラート(PPARα活性化β酸化↑TG↓LPL↑HDL↑apoA1↑)or PPARαモジュレーター(腎排泄性でないため、スタチン併用でも安全性高い。ペマフィブラート)Cr>2禁忌、>1.5少量投与
- PCSK9抗体 LDL受容体のリサイクリング↑
- MTP(microsomal triglyceride transfer protein)阻害薬ロミタピド。FHホモのみ。LDL↓TG↓
肥満症
肥満日本 男性30%,女性20% 臍レベルCT内臓脂肪>100cm2, ウエストM>85cm, F>90cm
肥満関連合併症11疾患はメタボリックシンドロームとはことなる。
DM患者のBMIは上昇傾向M24.5<F24.8(海外より低いが)
30,40代で高度肥満が増加
日本人は,欧米白人と比較して,同じ BMI で見ると, 脂肪肝の頻度,内臓脂肪面積,体脂肪率が高い
治療
- 肥満症 3-6か月で-3%減量
- 高度肥満症 5-10%減量
行動療法;セルフモニタリング、ストレス管理、刺激統制法(テレビ遮断)、問題点の抽出と解決、報酬による強化(成功体験、褒める)
肥満外科
- ラパロ胃バイパス
- スリーブ状胃切除(日本で一番多い2014/4保険収載、死亡率0.28%、スリーブ切除でGLP1↑)
- 胃バンディング
肥満症学会:18-65yの原発性肥満, BMI>35, BMI>32で糖尿病かつそれ以外の肥満関連合併症2つ
保険適応はラパロスリーブ:BMI>35, 6か月以上の内科治療、DM,DLP,HTN,SASのいずれかあり
追加、BMI32.5~34.9で糖尿病(HbA1c8.4%以上)かつ高血圧症(SBP≧160mmHg)、 脂質異常症(LDL-C≧140、nonHDL-C≧170)、SAS(AHI≧30)のうち1つ以上を合併している患者
小児肥満症
2017年4月ガイドライン策定。6-18歳。学童期においては肥満度20%~+体脂肪率M>25%,F>35%=小児肥満症
HTN、SAS,T2DM、耐糖能異常、内臓脂肪型肥満、早期動脈硬化症
or
肥満度>50%+NAFLD, IRI↑黒色表皮症、TC↑nonHDL↑、TG↑HDL↓、高尿酸血症1つ
or
肥満度<50%でも上記疾患2つあれば
治療は肥満度の軽減


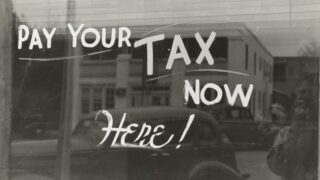





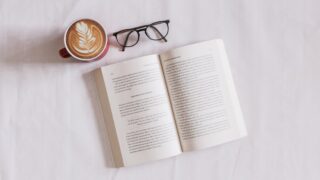



コメント